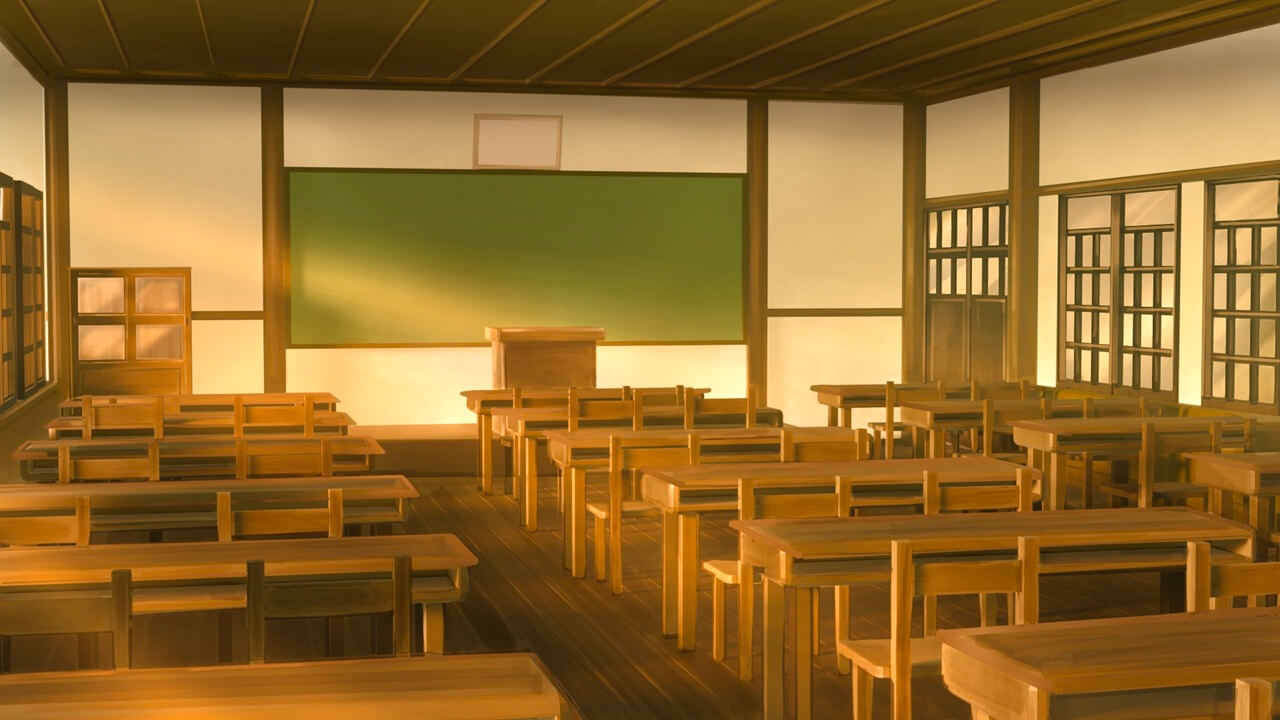卒業の時季と副題
| 時季 | 仲春 3月 |
| 副題 | 卒業歌 |
卒業の解説と俳句での活かし方
日本では、小学校から大学まで、ほとんどの学校の卒業式が3月に行われる。
ゆえに卒業は、仲春の季語とされる。
卒業や名を持つ星と持たぬ星
櫨木優子
胸高に袴きりりと卒業す
岸彩
卒業の兄と来てゐる堤かな
芝不器男
卒業のその後の彼を誰も知らず
藤松遊子
若者にとって卒業は、友や教師との様々な思い出(良い思い出も、忘れてしまいたい思い出も…)が詰まった学校に別れを告げる、青春の節目となる。
卒業といふ美しき別かな
清崎敏郎
劇に出て鼠の役や卒業す
田川飛旅子
ががんぼの一肢が栞卒業す
齋藤愼爾
同時に卒業は、気持ちを切り替え、場合によってはこれまでの鬱屈した日々を断ち切り、新たな自分の創造を始めるスタートラインにもなる。
洋々たる未来に向かう気持ちを俳句に詠みたい。
校塔に鳩多き日や卒業す
中村草田男
頬燃えて自画像出来ぬ卒業す
皆吉爽雨
一方、卒業生を送り出す教師にとっても、やはり卒業式は感慨深い行事となる。
そして、束の間ほっとした気分を味わったり、静かに感傷に浸ったりするタイミングにもなる。
卒業子去れり窓辺に教師暮れ
林翔
卒業生呼名授業の声でせり
凡茶
卒業式の締めくくりには、「仰げば尊し」「蛍の光」などの卒業歌が歌われるが、このときばかりは生徒も教師も、こみあげて来るものがある。
俳句には、卒業歌の場面を詠んだ作品も多い。
ゆく雲の遠きはひかり卒業歌
古賀まり子
卒業歌職去る歌と口ずさむ
山本美枝

季語随想
かつて私は、高校の地理教師でした。
常に自信を持てず、すぐに退職を考えてしまう、赤点の教師だったように思います。
しかし、三年生の担任として、卒業式の卒業生呼名に臨み、生徒の名前を一人一人読みあげているときだけは、教師としての自分をほめてやりたくなりました。
色もまちまち、長さもまちまち、先の尖ったのもいれば、丸くなったのもいる…
そんな生徒たち一人一人と真剣に向き合い、悩み、様々な判断を重ねてきた自分を、その時だけは、ちょっとだけ、ほめてやりたくなりました。
卒業や丈の揃はぬ色鉛筆
凡茶
おわりに
ここまで当記事をお読みいただき、ありがとうございました。
ところで、日本では、たびたび9月入学制度導入の議論が沸き起こります。
9月入学制度になると国際社会と足並みが揃い、日本から海外への留学、海外から日本への留学がともにし易くなるためです。
実現すると、卒業式は7月下旬、もしくは8月上旬となり、「卒業」は晩夏の季語、または初秋の季語となるでしょう。
教育制度の改革は、学ぶ者にとって最も良い環境を整えるためになされるべきであり、「グローバル化の中で、日本も9月入学に変更すべき」という判断で社会的コンセンサスが得られるならば、その方向で進むべきでしょう。
ただ、名残雪、桜のつぼみ、光る風などが彩る仲春の景と、卒業という行事とを結びつけて俳句を詠み、俳句を味わってきた俳人としては、卒業という語が春の季語でなくなることに、一抹の寂しさは覚えます。ですが…
まあ、卒業が夏休みの入り口と重なる季語に変わったら変わったで、俳人たちは、卒業の語を、梅雨明けの眩しさ、行く夏のセンチメンタルな気分などと結び付け、たくましく句を生み出していくのでしょう。
さて、最後になりますが、下に並べた「学業・ビジネスの季語」「3月の季語」などのタグをクリックすると、関連する季語を紹介するページが一覧で表示されます。
ぜひ、ご活用ください。