 俳句の作り方
俳句の作り方 切れと切字
俳句における「切れ・切字」とは何か。季語や定型と同じくらいに重要な要素である切れと切字について、例句を示しながら、丁寧に解説していきます。
 俳句の作り方
俳句の作り方  夏の季語
夏の季語  春の季語
春の季語  新年の季語
新年の季語  冬の季語
冬の季語 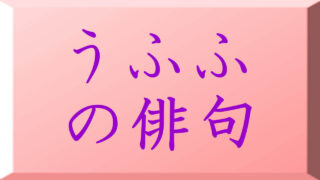 凡茶の俳話
凡茶の俳話 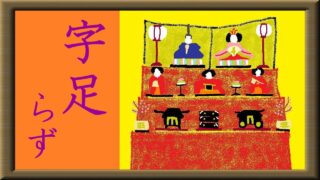 俳句の作り方
俳句の作り方  俳句の作り方
俳句の作り方  秋の季語
秋の季語  夏の季語
夏の季語