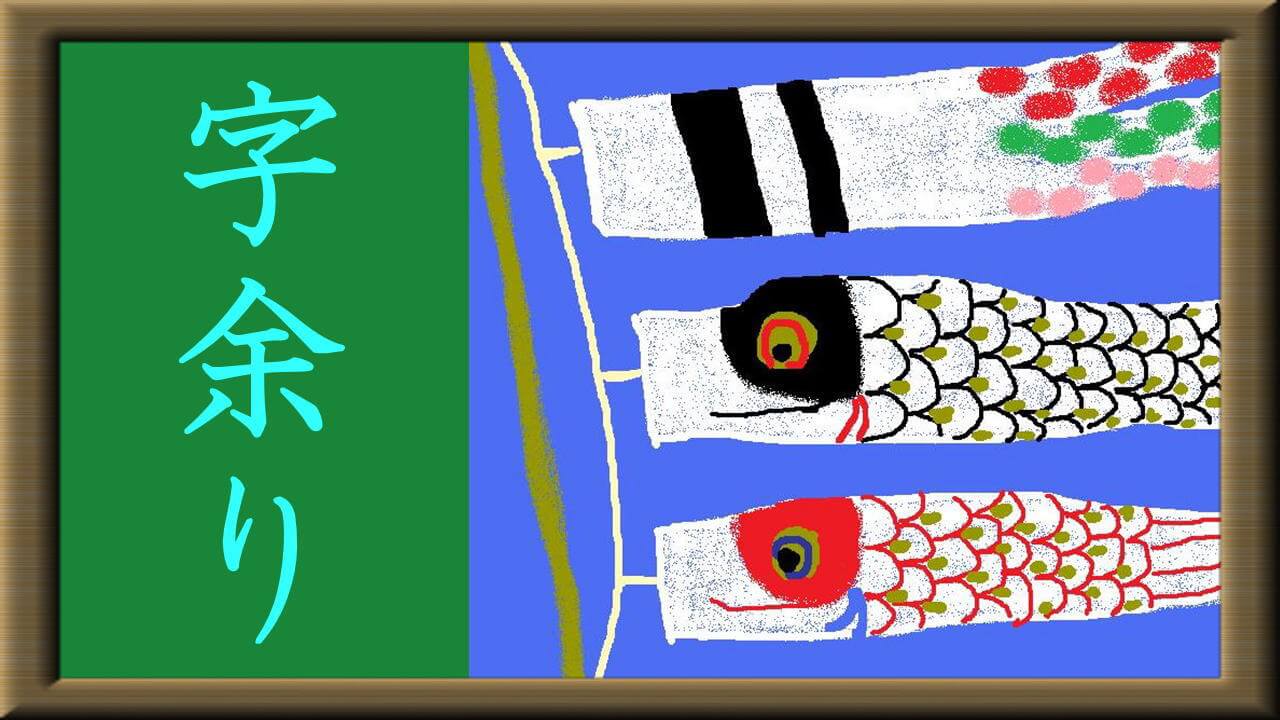字余り
俳句は五・七・五音で作るのが原則です。
この五・七・五音よりも、一句に含まれる音の数が多くなることを「字余り」と言います。
次の俳句は、私が若い頃に詠んだ作品です。
杖置いて朝凪の海拝みけり
凡茶
この句を、五・七・五の定型ではなく、あえて五・八・五や五・七・六の字余りで表現してみます。
杖置いて/朝凪の海を/拝みけり
(五・八・五音)
杖置いて/朝凪の海/拝みてをり
(五・七・六)
口に出して読んでみて下さい。随分、リズムが悪くなったことがわかるでしょう。
俳句は音を重視する韻文です。音を気にしない散文ではありません。
リズムが悪くては、俳句ではありません。
古くから和歌などの韻文で用いられてきた五七五音は、耳にすんなりと入ってくる美しい調べを持っています。
この調べを、安易に壊してはなりません。
ですから、字余りの俳句はできるだけ避けるようにしましょう。
私も初心者の頃は、一句に言いたいことをいろいろと詰め込もうとして、字余りの句を作ってしまうことがありましたが、結局気に入らず、捨てることになりました。
気にならない字余り
ただし、字余りの俳句が全て悪いというわけではありません。
五七五音の定型を守った俳句を読むように、自然に、心地よいリズムで読むことができるのならば、字余りも気になりません。
いくつか、気にならない字余りの例を見てみましょう。
撥音や長音を含む場合
これから他人の作った俳句を鑑賞しようとする読者は、その作品を五七五音の伝統的な調べに収めるように読もうとします。
そのため、俳句を鑑賞する気満々になっている状態の人に、「筋肉に痛みがあれば無理をせず」のような散文を読む機会を与えてやると、おそらく「筋肉に/痛みがあれば/無理をせず」という五七五音の韻文に変えて味わってしまうことでしょう。
この、俳句読者の「俳句を五七五音の伝統的な調べに収めて読もうとする習性」により、撥音(はねる音、すなわち「ん」)や、長音(「ー」などの伸びる音)を含む字余りの俳句が、ほとんど定型の俳句のように感じ取ってもらえるということがよく起きます。
拙句を例示するので、いくつか見てみましょう。
卒業や丈の揃はぬ色鉛筆
凡茶
この句の下五は、下記の通り六音で字余りです。
い/ろ/え/ん/ぴ/つ
しかし、俳句の読者は、撥音の「ん」を直前の「え」とセットにし、「えん」を脳内で一音に収めるようにして作品を味わってくれるでしょうから、この句における色鉛筆は、五音の語とほぼ同じ聞き心地になります。
い/ろ/えん/ぴ/つ
着せ替への吉良殿を欠く菊人形
凡茶
吉良殿:人形浄瑠璃や歌舞伎の演目となる『忠臣蔵』の主要な登場人物である吉良上野介のこと
この句も、下五が六音の字余りです。
き/く/に/ん/ぎょ/う
この語は、「ぎょ」と長音の「う」を合わせた「ギョー」と発音する部分がほぼ一音として聞いてもらえるため、おおむね五音と同じ聞き心地となります。
き/く/に/ん/ぎょう
あるいは、「に」と撥音の「ん」を合わせた「にん」を一音のように味わってくれる読者もいるでしょう。
き/く/にん/ぎょ/う
例示したような、撥音や長音を含む部分が字余りになっている俳句ができた場合は、その部分が定型と変わらない心地良い調べを生み出しているのか、否か、何度も声に出して句を読み、確かめてみることをお勧めします。
それで字余りが気にならなければ自信を持って作品として採用して下さい。やっぱり聞き心地が悪く、どこか耳障りだなと感じる場合は、定型を守る方向で句を修正する必要があります。
字余りの部分に撥音や長音が含まれ、ほぼ定型のように聞こえる句を、もう二つ掲げておきます。
缶コーヒーポケットに挿し鮪糶る
凡茶
春着子の輪の中に置く金平糖
凡茶
一句目は、六音の缶コーヒーが、撥音の「ん」と、二つの長音「ー」を含むため、ほぼ五音に聞こえます。
二句目は、六音の金平糖が、撥音の「ん」と長音の「う」を含むため、ほぼ五音に聞こえます。
上五だけが字余りの場合
まずは、次の例を読んでみましょう。
杖を置いて/朝凪の海/拝みけり
(六・七・五音)
上掲の「杖置いて朝凪の海拝みけり」をあえて六・七・五音で表現し直したものですが、五・八・五音の「杖置いて朝凪の海を拝みけり」や、五・七・六音の「杖置いて朝凪の海拝みてをり」よりは、聞き易かったのではないでしょうか。
上五だけが字余りになっている句は、冒頭こそ言葉が定型からはみ出しますが、その後、中七・下五は型どおりに読まれるため、一句全体を読み終えた印象は定型を守っている句に近いものとなります。
よって、同じ字余りの俳句でも、中七や下五の字余りほどは気になりません。
次の二句は、上五が字余り、中七・下五は型どおりの名句です。
牡丹散て打かさなりぬ二三片
蕪村
(六・七・五音)
厚餡割ればシクと音して雲の峰
中村草田男
(七・七・五音)
上五・中七・下五の字余りについては、以前に公開した上五・中七・下五の記事にも、詳しく述べておいたので、そちらもお読みいただけると嬉しいです。
なお、上五の字余りを、中七・下五の字余りほどは気にならないからと言って、多用するのは感心しません。
多くの場合は、定型を守った方が良い作品になると心得るべきです。
敢えてする字余り
ここまで「気にならない字余り」について述べてきましたが、俳人は敢えて「気になる字余り」の俳句を詠むことがあります。
松尾芭蕉が亡くなる四日前に残した、次の句を読んでみましょう。
旅に病て夢は枯野をかけ廻る
芭蕉
この句、「旅に病み夢は枯野をかけ廻る」と定型で詠むことも出来たはずですが、敢えて六音の字余りにして違和感を演出した「旅に病(やん)て(で)」の上五が読者の意識に引っ掛かり、季語の枯野よりも強調されています。
以下、字余りの違和感が、読者の注意を引き付ける「効果」として働いている名句を紹介します。
短夜や乳ぜり啼く児を須可捨焉乎
竹下しづの女
雪はしづかにゆたかにはやし屍室
石田波郷
囀に ぱちくり ぱちくり 梅の花
伊丹三樹彦
一句目は下五の「須可捨焉乎」が七音の字余り、二句目は上五の「雪はしづかに」が七音の字余り、三句目は中七の「ぱちくり ぱちくり」が八音の字余りですが、その部分が一句の中のクライマックスになっています。
おわりに
ここまで当記事をお読みいただき、ありがとうございました。
上に掲げた草田男の「厚餡割ればシクと音して雲の峰」の句ですが、この厚餡とは、どの和菓子を指しているのでしょうか?
饅頭か、きんつばか、それとも最中か?
この句、具体的な菓子の名を用い、「饅頭割れば…」「きんつば割れば…」「最中割れば…」と詠んでも作品として成り立ったと思うのですが、そこを明示せず、読者の注目を菓子そのものでなくて、中身の餡に集めたあたりが、非凡だなあと感じさせられますね。